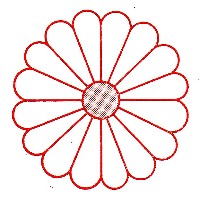  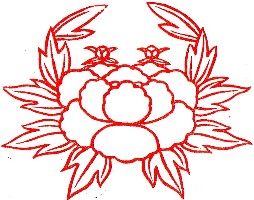 天台宗概要 |
||
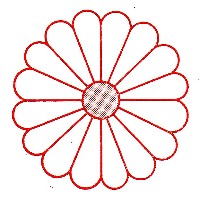  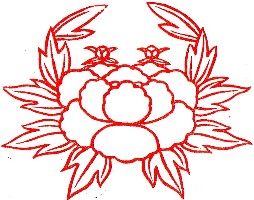 天台宗概要 |
||
| 仏教の中国への伝来は騎馬民族の時代であった。従来彼らが信じてきた土俗信仰を捨て、仏教を信仰するに至ったのは、当時の仏教が財政、建築、医療等々様々な最先端の知の結集だったとされ、漢族的な儒教の桎梏(しっこく:教え)が馴染(なじ)めなかったためともいわれている。 中国に伝来した仏教を体系化し、天台三大部を表わしたのが天台宗の祖といわれる智顗(ちぎ538~597)であり、天台三大部で智顗は教門(きょうもん)と観門(かんもん)の二つの法門(ほうもん)を基本とした。教門では「法華玄義(ほっけげんぎ)」十巻、「法華文句(ほっけもんぐ)」十巻を表わし、観門では「摩訶止観(まかしかん)」十巻を表わした。法華玄義(ほっけげんぎ)は法華経の教題である「妙法蓮華教(みょうほうれんげきょう)」の五字によせて仏教を解説したものであり、法華文句では法華経を天台の立場から解釈した注約書といえるものであり、摩訶止観は法華経理論の具体的な実践方法を説いたものといえる。智顗は悟りを開くための観法を禅ではなく止観(しかん)という言葉で表わした。 一方、奈良時代後期になると、日本の仏教は「南都仏教」を代表とするような、民衆とはかけ離れた僧たちの学問集団的な様相を強め、国家の庇護(ひご)の下での呪術的な祈祷などを行う程度になっていた。南都仏教から逃れ、平安に遷都(せんと)した桓武天皇を始めとして、新しい仏教の誕生が切望されていた。そこに登場したのが唐から帰国した二人の天才である。最澄が開いた天台宗、空海の開いた真言宗は、鎮護国家(ちんごこっか)の仏教から、民衆の仏教として変遷を果たし、得度(とくど)、受戒(じゅかい)を国家から取り戻した。民衆救済の仏教として、それは日本の第一次宗教改革と呼べるものであった。 最澄が唐に渡ったのは、803年(延暦22年)38歳の折である。途中暴風雨にあい九州に漂着したが、翌年九月に唐の明州に到着する。同行の一行とは離れ、一路、天台智顗が修行の場として選んだ天台山を目指した。途中で道邃(どうずい)から教学の書を与えられ、書写の便宜を図られた。十月に天台山入りを果たし、八十余巻の法門を伝えられ、大仏頂曼荼羅(だいぶっちょうまんだら)とその供養法や禅を授かる。翌年天台法門を書写し終えた最澄は、密教の灌頂(かんじょう)を受け、密教の経典も百五十巻書写し、その後帰国した。 最澄が開いた総合仏教としての天台宗では「円教、密教、禅、戒」の四宗融合を基本とした。円教では南都仏教が声門(しょうもん)、縁覚(えんがく)、菩薩(ぼさつ)の三つの乗り物(三乗)があり、菩薩の領域に達しないと成仏(じょうぶつ)できないとしていたのに対し、最澄は三乗の区別はなくすべての人は平等に成仏できる一乗であると説いた。こうした大乗仏教の起りは、出家修行したものだけが悟りを開けるとした仏教に対する批判からであり、誰もが悟りを開くことができ、一切衆生を救済しようという大乗こそが、利他の精神につながるものであるとした。 空海を開祖とする真言宗や後に誕生する鎌倉新仏教が、それぞれ密教であったり、禅であったりと云わば単科仏教であったのに対し、最澄を開祖とする天台宗は、前述のように四宗融合の総合仏教的存在であった。鎌倉新仏教と呼ばれる仏教の開祖たち法然、親鸞、栄西、道元、日蓮等々が挙って、比叡山で天台宗を学んだ意味がある。洋の東西を問わず真の改革は、民衆に視点を置いている。比叡山で学んだ鎌倉新仏教の開祖たちによって、仏教が民衆に一層近い存在になったに違いない。 |
| 願興寺所蔵重文仏像群 | 願興寺縁起(歴史) | 住職小川文甫の部屋 | ホームに戻る |